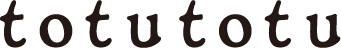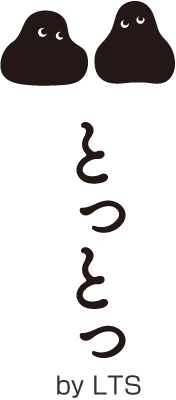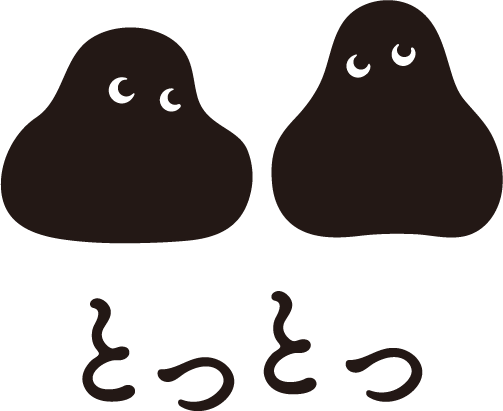81歳、まだまだ現役で活躍されている井村さん
生まれはね、昭和18年3月。戦時中に生まれてるんで戦中派って言うんですよ。81歳です。
井村屋の社長を卒業して、会長も卒業して、相談役も卒業したあと、まあフリーになったというか。その後教育委員会を8年、赤い羽根共同募金会の会長を8年ぐらいしたかな。そしたら声がかかって、今は社会福祉協議会の会長をさせてもらっています。もう10年以上になるかな。

父が戦友21名と作った「株式会社井村屋」
戦前の明治29年からね、僕のおじいさんが「井村屋」というまちの菓子屋をやってた。そこで作っていたお菓子は生菓子、つまり日持ちがしない、3日ぐらいで食べないといけないお菓子だった。親父は松阪商業を卒業したんだけど、学生の時分から家業の菓子屋を手伝ってた。その「井村屋」をじいさんから家督を譲られて、持っていたの。で、戦後の昭和21年に親父が継いで、33連隊(陸軍の部隊)の戦友21名と集まって株式会社井村屋を設立しました。戦後の井村屋は、戦前の生菓子じゃなくて、日持ちのするビスケットやキャンデー、キャラメルなんかを作って全国流通させようとしていったんだよね。

戦時中、松阪に家はあったんだけど、空襲で危ないってことで、小さい頃はおふくろと一緒に田舎の方に疎開してました。でも、松阪は戦災に遭わなかった。「もう明日来るか」という状態の時に終戦になった。そこに井村屋の本社があったんです。
その頃、本社のあった新町地域の家は、どこも細長かった。昔は家の間口の大きさで税金を取られたからね、間口を狭くしたんです。入口が細くて奥が長い。その細長い一角に僕の自宅もあったわけね。
自宅の後ろに本社工場があった。砂糖だとかの荷物が重くて持てないから、20mか30mくらいあるトロッコをつくって、工場まで運んでた。友だちがよくトロッコに乗りに来たりしてたね。
本社を津市の高茶屋に移した後、狭かった自宅兼本社工場前の道も広くなりましたね。その時に全部変わっちゃって、昔の面影は今は全然ない。

現在の松阪市新町通りの様子
津工場というのは海軍工廠(こうしょう)の跡。海軍工廠というのは海軍の工場みたいなものね。飛行機とか鉄砲の部品なんかをつくった工場です。それが高茶屋にずらーっとあった。機械とかは一切残ってなかったけど、建屋だけは全部残ってました。その建屋のまま、中だけ機械を入れて工場に変えました。
昔の工場は木造でね、ほとんどがのこぎり屋根になってた。当時はやっぱり電気代が高かったんでしょうね。節電のためにできるだけ太陽光が入るようになってた。

(井村屋グループ株式会社提供)
津工場の周りは砂利道で、馬車が荷物を運んでた。日本通運の馬車もあったね。道路は馬糞だらけだし。それに段ボールもない時代だから、木枠か荒縄で荷物をまとめて運んでたね。荒縄の縄は稲わらでつくってあるからきれいな縄じゃない。僕も稲わらで草履とか自作してたね。僕らは小学校に入るまでは草履だった。だから運動靴を履けるのが、もう嬉しくてしょうがない。枕元に置いて寝たりしてたね。
建物も人も時代とともに変わる
津工場は徐々に新しくしていったんだけど、事務所棟は長い間、のこぎり屋根を残してた。もったいないというか、歴史の記念物だからって。昔の工場は戦時中に木造でつくったやつでしょ。つくり方があんまり丁寧じゃないから雨漏りとか大変だったんだけどね。建て替えたのは十数年前じゃないかな。やっぱり火災や地震だとか、いろんな規制があって残せない。それで建て替えちゃいましたね。

僕は小学校のときから松阪でずっと育ってて、松阪での風習とか習慣とかが染みついてますね。昔は向こう三軒両隣の内情のことも知ってたし、そういう時代だったなぁとつくづく思います。
例えば、うちは商売やってたから電話があったけど、普通のお家には高いから電話はない。だから「呼び出し」をするんです。例えば、あなたの家は電話があって、僕は隣の家なんだけど、電話がない。そうするとあなたの電話番号が300番だとすると、僕の名刺に「300番呼び出し」って書く。そうするとあなたのところに電話がかかってきて、「隣の井村さん呼んで」って。で、あなたが「はいはい」って僕を呼びに来る。お金を出させるわけでも何でもない。僕も、「ああ、ありがとう。また使わせてね」でおしまい。
昔は電話もそうだし、仲間内で定期的に集まってお金を出し合い融通する「無尽」という仕組みもあった。そこで得たお金で商売を始めたりとかね。この仕組みが相互銀行のもとになってるんだよね。こんなふうに隣近所というものがないと生活が成り立たない。やっぱり、助け合いの気持ちっていうのは、そういうところから当然出てくる。あの人は奥さんがこんな人で子どもが何人いて、今どこに行ってるっていうことを全部必然的にお互いが知り合う。昔はプライバシーがなかったからやっぱり絆は強かったんだろうね。そういうのは本当に懐かしいよね。

ライフ・テクノサービス採用担当。主に中途採用の担当として面接や面談を実施しています。
2歳の男の子がいるワーママです。仕事に家事・育児にと毎日フル稼働しています!