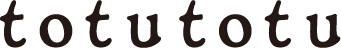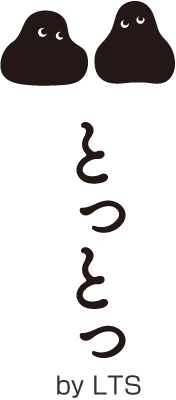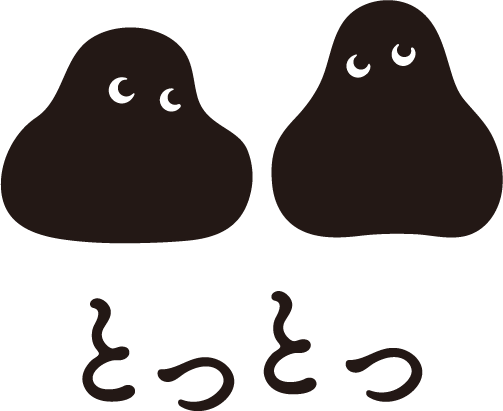老年だったあの人と、若かった私の風変わりな思い出たち。
tayutaiはいろんな人が執筆する、思い出のコラムです。
よく晴れた、ある朝。
なんだかサッパリしてしまいたい気持ちに駆られて、起き抜けに掃除をしてゴミを出しに行った。ゴミ置き場の横には自販機があって、色は青。
真っ青な自販機を見ると、たまに思い出すことがある。
京都のおばあちゃん、と呼んでいた、父方の祖母のこと。
とりとめもない、だいすきなおはなし。
父方の祖父母は京都に住んでいた。祖母はのんびりとした話し方(いわゆる京ことば)で良く喋り、いつも身綺麗にしていて祖父ととても仲が良かった。
祖母は高校の英語教師をしていて、父が子供の時分は当時大学の准教授だった祖父の代わりに家計を支えていた。(国立大の准教授は儲からなかったらしい)
祖父の母(祖母からみると義母)に家事育児を託し大黒柱として働いていた祖母は、当時にしては珍しいバリキャリママであった。
あまりの指導の厳しさに、生徒からは「鬼のヒラオカ」と呼ばれていたらしい。(ちなみに現在私も会社でたまにそう呼ばれている、血は争えない?)
祖父が教授となった折に祖母は教師を引退したが、祖父の学会に同伴する場面などで、培った英語力を発揮していた。
欧米では学会の開催国に夫婦で訪問し、夫の教授陣が学会に出席している最中は奥方陣は連れ立って出かけ交流を深めるのだそうで、祖母は英語が話せるので1人放っておいても上手くやってくれているのがありがたい、と祖父は感謝していたそうだ。
祖父の仕事がひと段落して、ようやくのんびりと夫婦の時間を、という矢先に、祖父が突然亡くなった。
祖父が亡くなってから暫くして、祖母は老人ホームに入居した。
ホテルのような豪奢な施設で、たくさんのアクティビティや広い部屋、綺麗なレストランなど、羨ましい限りの環境だったのだけれど、祖母は寂しかったようだ。
そのうちに、実子である父と叔母に何度も電話を架けるようになった。
段々と電話を架けたことを忘れ、電話を切ったらまたすぐに架けてくるようになった。父と叔母は、段々と電話に出る回数が減っていった。
老いとは、積み上げてきた様々を奪うらしい、と、その時の私は思っていた。
ある冬の昼下がりだったと思う。
家族で祖母を訪ね、一緒にホームの廊下を散歩していると、なんの話でそうなったかは忘れてしまったが、祖母がアレは何だったか、と忘れてしまった言葉を思い出そうとし始めた。
「なんやったかねえ、あの、アレよ、アレ」
なんだろう、と私と弟は交互に当てっこをする。
「アレよ、機械の」
「パソコン?」
「せやなくてなあ、あの飲み物が入ってる」
「あ、冷蔵庫?」
「せやなくてねえ、何やったかねえ、アレよアレ」
祖母は自分の頭の中を覗いて、漸くピン!ときたらしい。
「ああ、思い出したわ、アレやわあ」
「え、なに?」
「アレやわぁ、アレ」
「Vending machine!」
祖母の口から唐突に、恐ろしく流暢な英単語が飛び出したのだ。
アレに対するアハ!体験も吹っ飛び、京ことばからのキレのよい英語(Vの下唇噛みからのAのエの口でのア発音)への急カーブぶりに、
「おばあちゃん、なんでいきなり、英語なん!」
と弟と大笑いをした。
祖母はいつもののんびりとした口調に戻り、
「おばあちゃんなあ、英語の先生、してたんよ」
と言った。
「忘れへんもんやねえ」
祖母は私たちの背中越しをじっと見て、半ば独り言のように言った。
振り返ると、廊下の先には青い自販機があった。
祖母の部屋に戻ると、母にVending machineの話をした。
すると母は「おばあちゃんね、学会で知り合ったお友達と今でも英語で文通してるんだよ」と教えてくれた。
私は初めて、雑多だと思っていた祖母の机に英字の手紙が置いてあることに気づいた。海の向こうの旧友とのやりとりだった。見事な筆記体は想いを乗せて、するすると紙を縫って、踊っている。
私はこの日、祖母がなにも奪われていないことを知った。
祖母の人生は、これまでから今も、実はずっと地続きで、ひらりひらりと積み重ねた様々なもののうえに、確りと立っているのだと判った。
そのあと少しして、ある日突然亡くなって、祖母の人生は終わった。
けれどもわたしは今日みたいに、あのVending machineを思い出す。青い自販機を見るとたまに。ひらりひらり、と、祖母を思い出す。

寄稿者:UMI
改善の仕事をしながら、たまに物を書いて暮らし、ひそひそプレスで仲間とZINEをつくっています @hisohiso_press
この度はとつとつ様にお声がけいただき、僭越ながら寄稿させていただきました!素敵な機会をありがとうございます

少子高齢化や人口減少、そしてデジタル化がすすんでいるのに、自分たちが暮らすまちのことはあまり知らない。ふと我に返ったとき、むかし祖母に聞いたまちの想い出話を、無意識に思い返していた。
そうだ、きっと自分が暮らすまちに誇りを持てていなかったんだ。ならば人生の先輩方に聞けばいい。まちにとって想い出はなにより大切な資産だと思うから。
自分が暮らすまちが少しだけ好きになるように「とつとつ」と語っていきます。お付き合いいただければ幸いです。